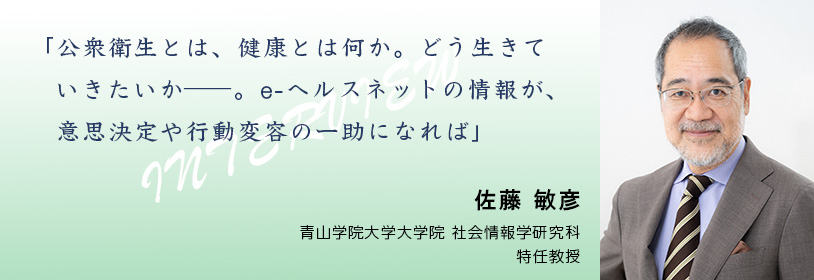
e-ヘルスネットは、健康情報の専門家と、掲載コンテンツ10分野それぞれの専門家である「情報評価委員」10名の指示や承認のもと、情報提供を行っています。このコーナーでは、情報評価委員の先生方から、ご専門の内容やe-ヘルスネットに対する思いなどを聞かせていただきます。
今回お話をうかがったのは、2007年の創成期から長きにわたってe-ヘルスネットにご尽力くださり、副座長も務めてくださっている佐藤敏彦先生です。「e-ヘルスネットはこんな人たちが作っているんだな」と身近に感じていただけたら幸いです。(2023年9月取材)
私の専門の「公衆衛生学」というのは、なんとなく耳にしたことはあるものの、「ではどういうものか」と問われると答えられないのではないでしょうか。公衆衛生という考え方と名称が広まったのは、第二次世界大戦後からです。実はこの学問、説明にもとらえ方にもすごく難しいところがあって(笑)。あえてひと言でいうと、「どうしたら“人々”を健康にできるか」を考えることなんです。
ここでポイントになるのが「人々」。医療、すなわち臨床医学では「個人」に着目して、目の前にいる患者さんをどうやって健康にするかを考えますよね。一方、公衆衛生学では人々、つまり「集団」をどうやって健康にするかを考えます。最大公約数なのか最小公倍数なのかはわからないけれど、多くの人にとっての全体の「最大値」を求めるのが公衆衛生なのです。
最大値を求めるには、「何がいちばん重要な課題なのか」という優先順位づけがとても大切です。たとえば、世界保健機関(WHO)の目的は「Health for All」つまり「世界中のすべての人に健康を!」ですが、健康課題というのは当然、地域によって変わってきますから。優先順位をつけるには、必ず「ゴールをどこにするか」を決めて、明らかにしておく必要があります。
公衆衛生の目的が「集団の健康の増進」であることはおわかりいただけたと思います。でも、ここにはまだはっきりしていないことがありますよね。目的に向かって進むためには「集団とは誰のことか」「健康の定義とは何か」といったことを明確にしなければなりません。
かつては公衆衛生の目標は「平均寿命の延伸」つまり「長生き」でした。それが、社会や環境、価値観の変化などに伴い、次第に「Quality of life(QOL:生活の質)が重要」という考え方になっていき、そして、その結果として「健康寿命」という言葉が登場しました。
QOLを集団の健康度の評価に使用する必要性が取り上げられるようになったのは、まさに私がWHOに在籍していた1990年代の終わり頃。当時のWHOの事務局長にノルウェーの首相も務めたグロ・ハーレム・ブルントラント(Gro Harlem Brundtland)氏が就任し、「エビデンス(科学的根拠)に基づく保健医療政策」を打ち出してからのことです。「限られた資源」を有効、かつ、関係者のコンセンサスを得て使用するためには皆を納得させるエビデンスが必要なんですね。その政策の実現に向けて、WHOのなかでエビデンスを明確に形作っていく部局が創設されました。それが、私の在籍していたWHOジュネーブ本部の「政策と情報のためのエビデンス局」です。局長には、元・米国ハーバード大学教授のクリストファー・マレー(Christopher Murray)氏が抜擢されました。
政策と情報のためのエビデンス局は「世界の人を健康にするためにはどうすればいいか、エビデンスに基づいて考える」という役割を担っていました。そのために世界各国からデータを集め、分析し、優先順位をつけていくのです。もちろん、それまでの様々な保健医療政策がエビデンスに基づいていなかったのかというと、決してそういうわけではありません。ただ、データが圧倒的に不足しているために不確かさの残るエビデンスも少なくなかったのは、残念ながら事実なんです。
WHOの2000年の年次報告である『ワールド・ヘルス・レポート2000』では保健医療システムがテーマとなっており、その中で初めて「健康寿命の世界ランキング」が発表されました。そのランキングで、日本は「平均寿命」だけでなく「健康寿命」も世界一に輝いたのです。それ以降、健康寿命というキーワードは国内のメディアに大きく取り上げられ、広く知られるようになりました。
ところで、WHOでは健康寿命をどのように算出しているのかについてふれてみましょう。WHOの健康寿命であるHALE(Healthy life expectancy)は、DALY(Disability-adjusted life year:障害調整生存年数)という指標の裏返しともいえる副次的なもので、日本国内での健康寿命の定義と算出方法とは異なります。
DALYの考え方とは、完全な健康でいられる期間と、何らかの障害をもった期間を引き換えとしたら、どのくらいの値が釣り合うかを想定して、その障害の程度を決定し(障害係数といいます)、性、年齢、地域、疾病別に「健康損失」を数値化しようとするものです。ここでいう障害とは、たとえば偏頭痛や喘息、四肢麻痺、うつ病など、多岐にわたる「健康ではない状態」を指しており、障害がより大きい場合に1に近く、障害がないと0になります。
DALYという単位を使用すると病気やけがによる様々な健康損失の程度が性別、年齢別、地域別にはっきりと比較することができます。たとえば、発展途上国の場合には感染症による障害・死亡や、栄養不良による障害・死亡による損失が大きく、先進国の場合には生活習慣病やうつ病による損失が大きいといった状況がわかります。「健康損失の大きさ」と「介入施策による改善期待度」により、優先順位や必要な支援が明らかになるのです。
ただし、この指標には当初から様々な批判がありました。その一つが障害係数の決定方法です。うつ病による障害と喘息による障害を比較して数値化するのって、想像しただけでも難しくありませんか? いろいろな方法を工夫・改善しているものの、実際、なかなか難しいですよね。
WHOでは私自身、エビデンスを確立するために「どういう障害の人が、どんな地域で、どのくらいの性・年齢別にいるか」を推定する仕事に携わっていましたが──果たして、世界中にそんなデータはあるとお思いですか。
日本国内に絞ったとしても、たとえば「現在のうつ病患者さんの正確な人数」はわかりません。「人口動態調査」の死亡統計によって、死因別の死亡数は何とか知ることができます。ですが、今この瞬間、特定の病気で苦しんでいる人がどのくらいいるかというのは、調べようがないのです。なので、様々な調査や研究から様々な仮設を立てて推定していくのですが、まあ、言ってみれば恐竜の化石のひとかけらから恐竜全体の骨格標本を作るようなものですね。
このように、すべての人が心から納得できる健康政策を打ち出すことの難しさを感じながら、私はWHOの職務を終えて帰国しました。とはいえ、帰ってくると当然「WHOの第一線で、エビデンスに基づく保健医療政策に携わっていましたよね?」と国内での貢献を期待していただけることもあり、内心のもやもやした気持ちはさておき、がんばらなきゃな、と思うわけなんですが(笑)。
帰国後は北里大学医学部に籍を置きながら、日本医療機能評価機構に設置された「EBM(Evidence-Based Medicine:科学的根拠に基づく医療)普及推進事業(Minds:マインズ)」の事業部長を務めることになりました。e-ヘルスネットの情報評価委員会座長・中山健夫先生にも、この事業部の委員として協力していただき、私がMindsを離れた後も中山先生にはMindsを発展させていただきました。
Mindsの目的は、当時必ずしもエビデンスに基づいているものばかりではなかった診療ガイドラインを見直し、各学会に働きかけて質の高い診療ガイドラインの普及・促進に努めること。そのような「科学的根拠に基づく診療ガイドライン」策定のために、どのようにデータを収集し、エビデンスを確立するかを明確にしながら、診療ガイドラインの作り方を体系立てていきました。
診療ガイドライン作りは、「こういう場合、●●することは正しいか?」といった臨床上の疑問(clinical question)を集め、それに個々に答えるためのデータを収集・精査するところから始まります。また、エビデンスを集めるために多数の論文に当たるのはもちろんですが、論文は「集めて、読んで、まとめて、それでおしまい」というわけにはいきません。きちんとした雑誌に発表されている論文がすべて正しいわけではありません。質も内容も様々なので、評価基準や、アブストラクト(abstract:論文の要旨)のまとめかたの指針を策定し、適正な評価を行う必要がありました。こうした診療ガイドライン作りの過程で、各専門分野における臨床医の先生と疫学研究者の「コラボ」が実現したのは、我が国のEBMにとっても画期的な出来事でした。
診療ガイドラインの策定と並行して進めていたのが、エビデンスづくりに必要なデータそのものを収集していく作業です。当時、私は北里大学で医学部付属臨床研究センターの創設に関わり、臨床研究の推進に取り組み始めていました。そして、さらに国内へと広く目を向けたとき、特に医薬品の開発における臨床研究を進めるには、臨床研究を行う医師や、疫学や統計に詳しい臨床研究の支援者を増やす必要があると感じたのです。そこで、中山先生ら数人の先生方とともに、保健医療情報分析活用研究会(現・一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所)を立ち上げました。
研究会で主に扱っていたのは、診療報酬明細書(レセプト)※のデータです。それまでは、レセプトのデータを利用したり分析したりする研究者はあまりいませんでした。というのも、当時のレセプトは紙だったので、データ化して収集・分析できるようにするためにはとんでもない労力がかかったんですよね(笑)。しかし、この紙のレセプトを電子データ化してビジネスにしようとした会社が現れて、これは利用させていただくしかないな、と思ったわけです。それ以上に問題だったのは、当時、レセプトデータは実態を表していない、ということで、なかなか論文を掲載してもらえないということもありました。そこで、われわれは会社とも協力しながら、レセプトデータがエビデンスに使用できることを徐々に明らかにしていったんです。レセプトの電子化に伴い、今では国もレセプトデータを積極的に利用するようになりました。
※保険医療機関が、保険診療でかかった費用を保険者に請求するために使用する書類。医療機関が患者さんに対して行った医療行為や傷病名、薬の処方内容などがわかる。
こんなふうに、私はあまりほかの人がやりたがらないことに取り組むことが多いんです。もしかしたら根があまのじゃくなのかもしれませんね(笑)。すでに誰かが取り組んでいて、自分がいなくてもうまくいっているところだと「じゃあ、その方にお任せしよう」と思ってしまうんです。医学部卒後に公衆衛生を専門として選んだのも、同じ想いだったような気がします。
e-ヘルスネットのテーマである生活習慣病予防という観点での「食事・運動・休養」「ストレスをためないこと」「何をすれば生活習慣病になりにくい」「より健康になれる」といったエビデンスは、すでにたくさんありますよね。でも、人によっては「運動はできない、したくない」とか「食事は絶対に変えられない」など、どうしても「譲れないもの」がある。そもそも、皆さんは年齢も性別も、仕事の有無も職種もバラバラ。そんななかで「こうしてください」「ああしてください」という、通り一遍の保健指導を行っても、受けた人全員が本当に「はい、これから生活習慣を改めます!」といって素直に実行できるかというと……やはり難しいでしょうね。
理想は、その人ごとの価値観やライフスタイルに寄り添って「じゃあ、運動はこうやって、そのかわり食事をこういうふうにしましょう」というように、多様性に富んだアドバイスが提示されること。保健指導ではもちろん、保健師さんが対象者の方とよく話し合ったうえで個々の最適解を提案されているとは思いますが、e-ヘルスネットも健康や生活習慣に関わる情報提供のみならず、意思決定や行動変容の一助になればと願っています。
私が青山学院大学で受け持っている「健康社会情報学」という科目では、受講生一人ひとりが、「自分の力で情報を収集・分析し、自らが納得できる意思決定ができるようになる」ことを目標にしています。最近のわかりやすい例を挙げると「新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種するか、しないか」でしょうか。人がどういっているかではなく、自分が納得してどうするかを決められるようになることは、人生の中で非常に大切だと思っているんです。
そのためには、様々な情報に当たって、自分の価値観に基づいて判断できればベスト。e-ヘルスネットのような健康情報サイトを読むのも一つの方法です。情報というのは、できるだけ加工されていないもの(一次情報)がいちばんいい。ですから、情報提供者としては、自らの見解を示したいのもわかりますが、素材を生かした料理を提供するように、なるべく操作されていない、客観性の高い情報の提供を目指すべきでしょう。
私は医師という職業柄、いろいろな方から様々な健康相談を──たとえば死に直面した方からも、受けることがあります。そんなとき私は、「どのように考え、行動すれば納得して人生を終えるか」ということに思いを巡らせ、自らにも問いかけます。
私自身についていえば、「すべてをやり尽くした」と思うことは、おそらく生涯ないでしょうね。だけど、どこかで何らかのゴールを決めておいたら、集団であっても個人であっても、いつだってよりよい方向に変わっていける可能性がきっとあるはず。そうすれば、いつか訪れる人生の終焉に向き合わなければならないときも、「ある程度は達成したな」「ある程度は楽しんだよね」と思えるような気がします。
私たち一人ひとりが、価値ある人生を、その価値を高めるためにはどうすればよいのかを、自らが理解して、まわりもそれを支援していけるような社会になったら最高でしょうね。そうした個々の価値を高めることが、集団全体の価値を高めることになりますから。だからこそ、個と集団の対立する価値をなんとかして一致させることができないだろうかというのが、公衆衛生に足を踏み入れてしまった私の永遠のテーマなんです。主観と客観の関係もそうですね。
健康とは何か──。真剣に考えてみますとね、医師であろうと疫学の専門家であろうと、やはり答えるのは難しい。この問いの答えを、これまでも多くの人が悩んできたんですよね。健康指標とは何か。どんな指標がふさわしいか。そうしたなか、苦肉の策としてDALYや健康寿命という考え方が出てきたんです。時には「ちょっと強引なんじゃないかな……」と思えるようなものであってもね。
では、なぜ無理にでもそういった考え方を出してくる必要があるかというと、集団の健康政策を考えるためには、やはりどうしても一定の指標を作らざるを得ないからです。健康の定義がブレてしまっていては、集団の健康について考えることなど到底できませんものね。とはいえ、その集団を構成している「個人の健康」は、人それぞれ違っていて当然なんです。
対立する「個人/集団」「主観/客観」のせめぎあいは、未来永劫続いていくもの。だからこそ、個人の視点で見たときと、集団の視点で見たときとでは、意思決定に違いが出てきてしまうんですね。もっというと、同じ人でも、20歳のときと70歳のときの視点、仕事をしているときと引退したときの視点で変わってきます。
私は自分の性格を、おおざっぱでいいかげんなほうだと思っています。ところが、一方では「いいかげんなままにしたくない」という気持ちもすごくあるんですよね。理路整然と「こういう理由で、だからこうなります」と考えたり口にしたりしたいんだけど、でも世の中そのものが理路整然とはできていないし、いいかげんなところもたくさんあるから、いいかげんにせざるを得ない。そのなかでもがきながら、何とかして「いいあんばい」を探したいと思っているんです。
率直にいって、私自身まだわからないんですよ──「健康とは何か」も、「どう生きていきたいか」も。現在の健康状態のまま「太く短く生きたい」と思っていても、もし病気が見つかったら「やっぱりもっと長生きしたい」と思うかもしれません。そうやって、どうすれば「いいかげん」が「いいあんばい」になるのか、「自分自身が納得できる」と「多くの人に納得してもらえる」のちょうどいいところが見つかるのか。そうした問題に、日々向き合い続けています。

佐藤 敏彦(さとう としひこ)
青山学院大学大学院 社会情報学研究科 特任教授
担当カテゴリ: 健康寿命
1986年慶應義塾大学医学部卒業。米国ピッツバーグ大学公衆衛生大学院修了、同研究員、東京女子医科大学公衆衛生学講師、世界保健機関ジュネーブ本部「政策と情報のためのエビデンス」局サイエンティスト、北里大学医学部公衆衛生学教室准教授、同臨床研究センター教授を経て現職。一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所理事長(兼職)、厚生労働省「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」委員。専門は公衆衛生学、特に疫学、健康情報学。
(最終更新日:2024年1月10日)